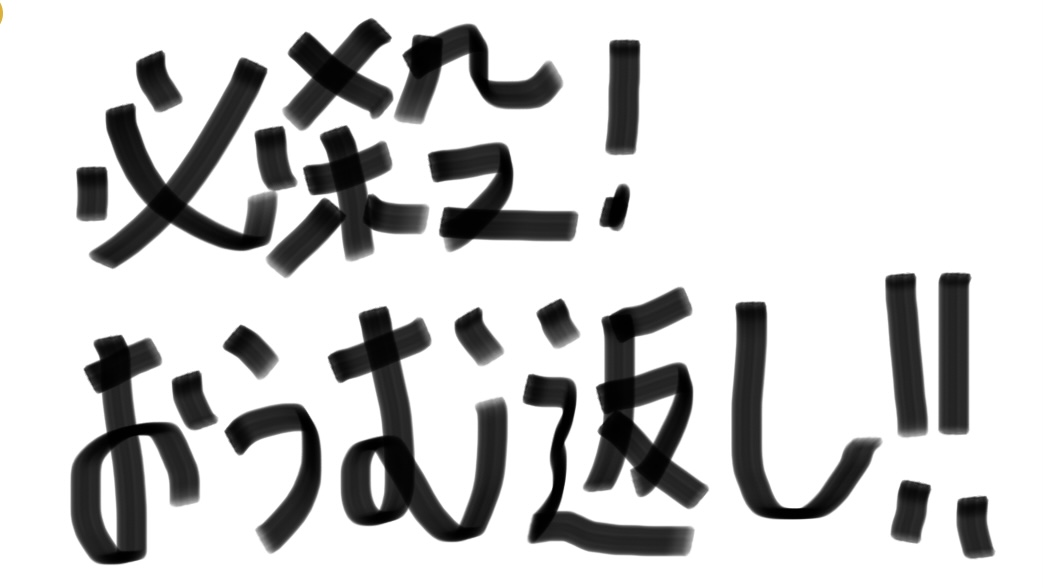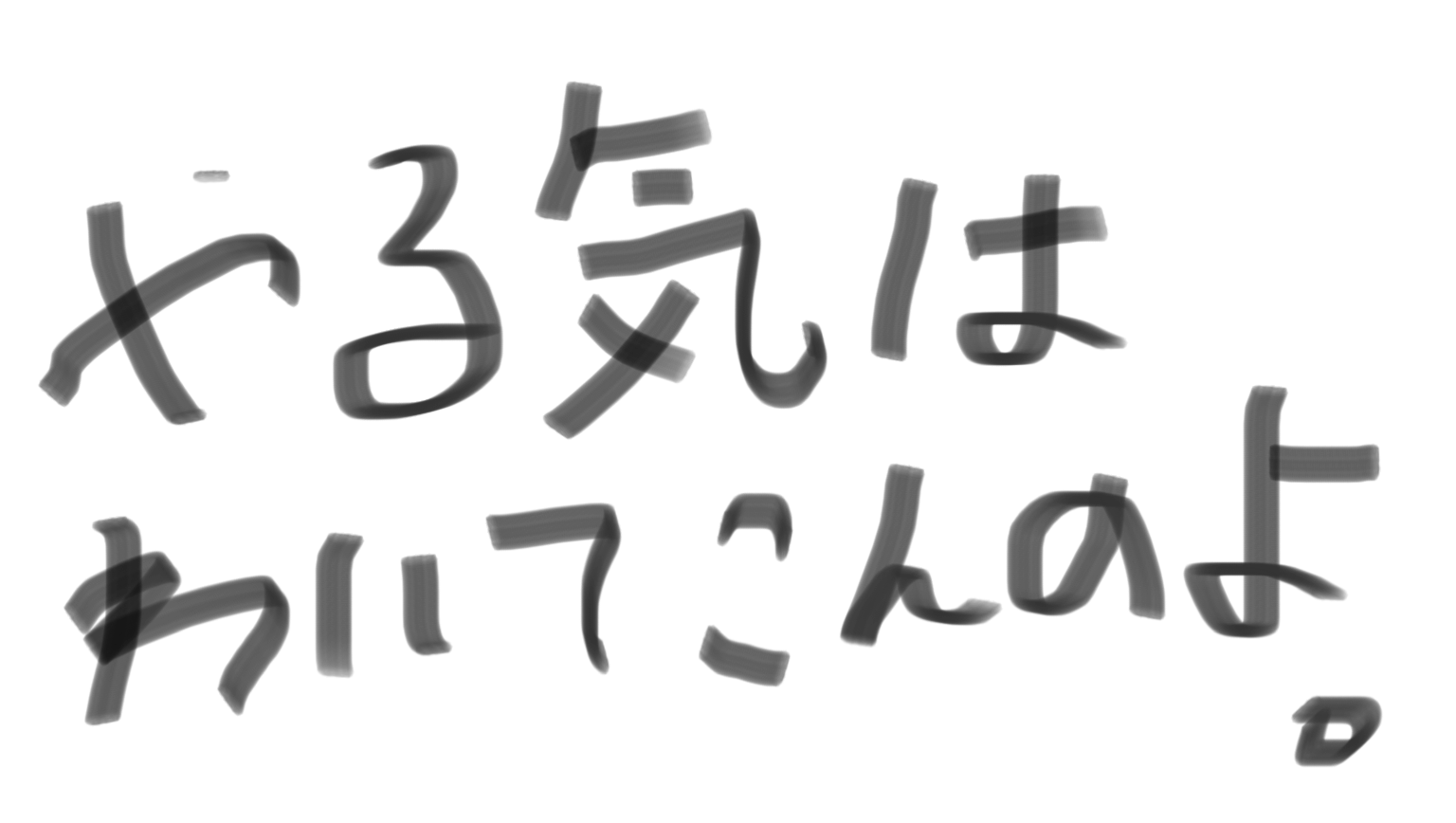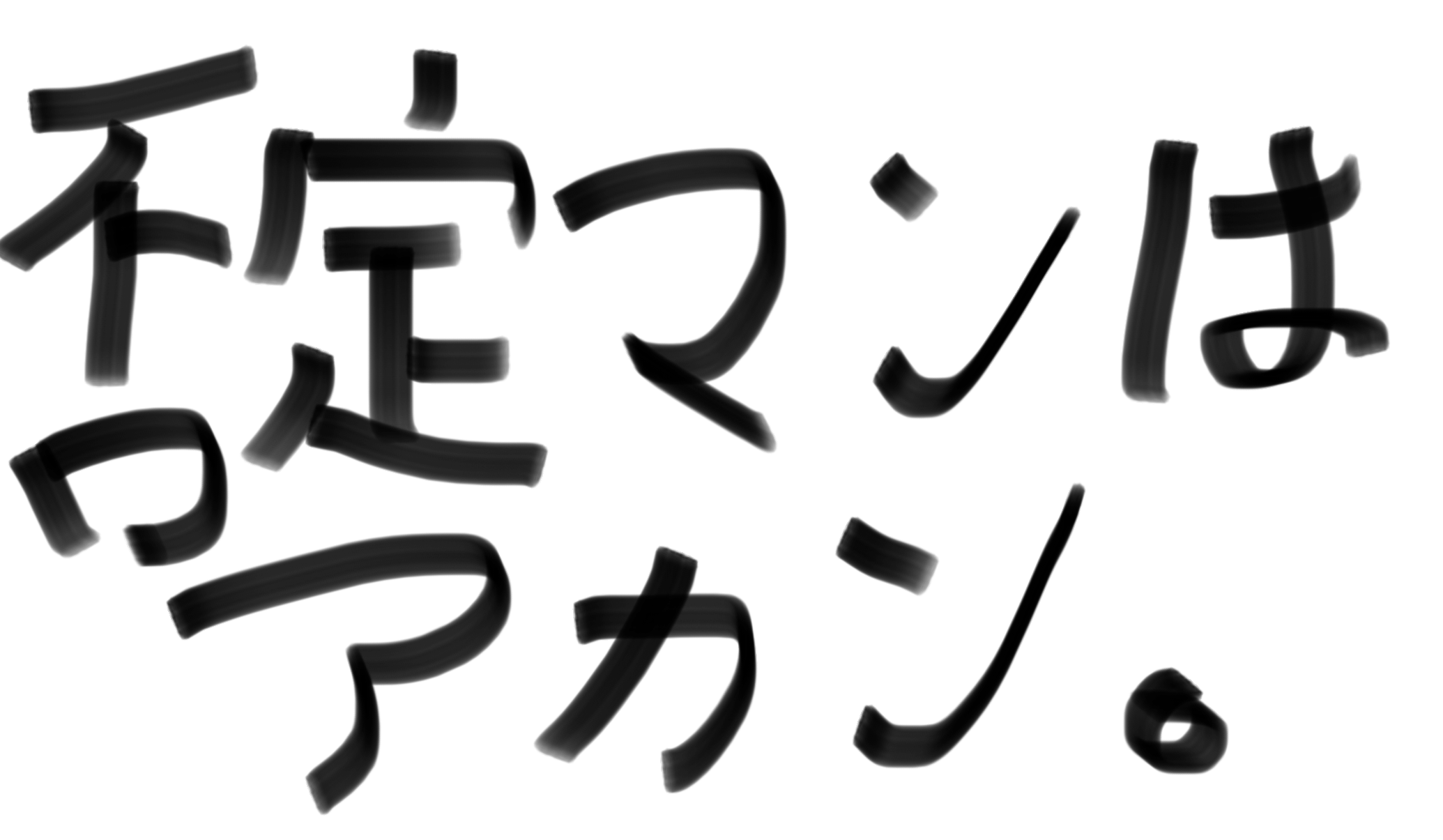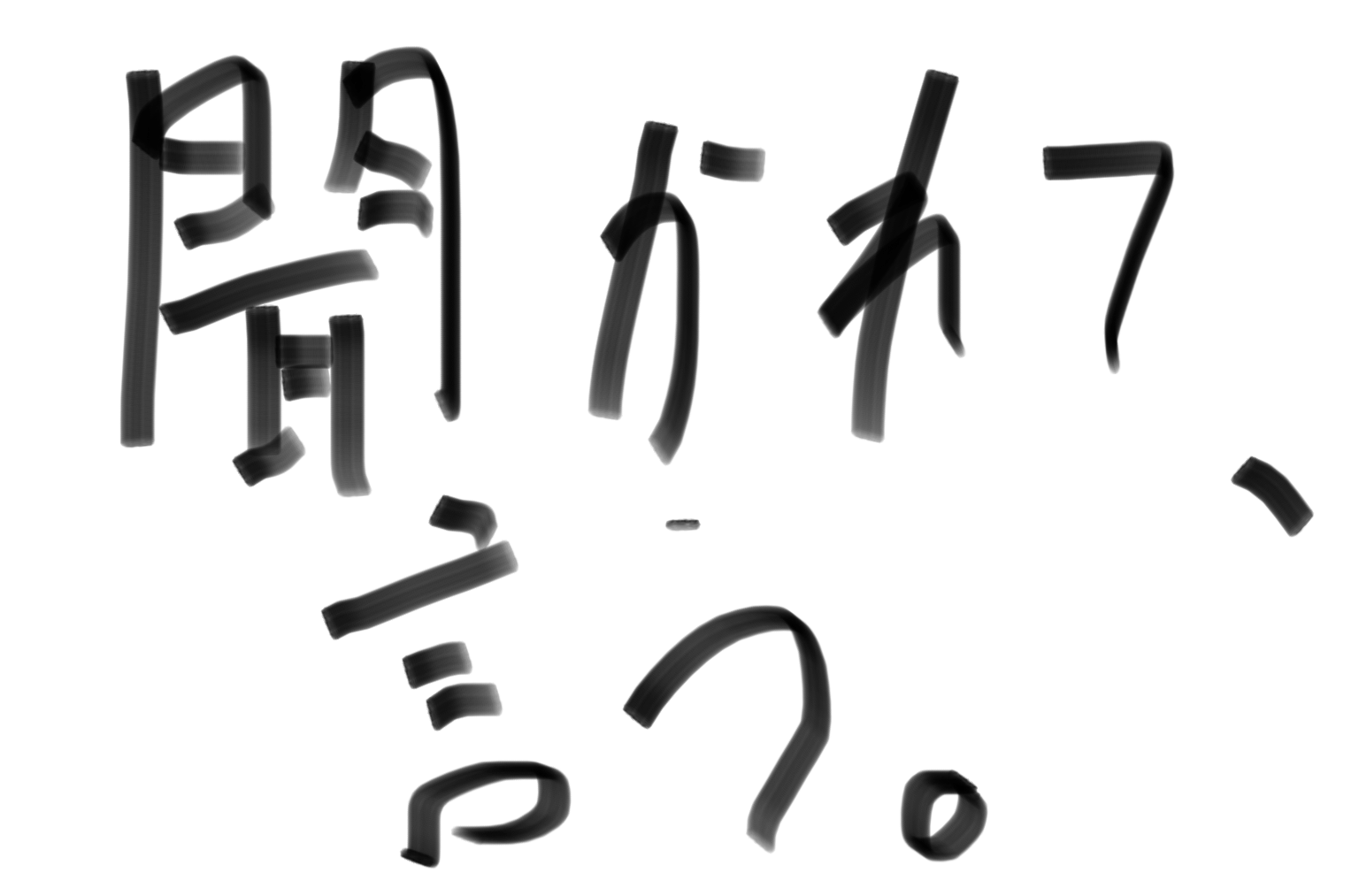読みやすい文章を作るためのコツとは?
「もっと文章力があれば…」と思いませんか?
例えば、こんな悩みはありませんか?
- SNSでフォロワーを増やしたい!
- LINEの文章が長くなりがちなのが、自分でも分かるからイヤ!
- 仕事で資料やメール、報告書などを、もっとうまく作りたい!
- これから副業として、ブログやWebライティングを検討中!
- ブログやWebライティングのスキルアップを勉強中!

「そうそう!」というあなた。
よく分かります。
「文字でわかりやすく伝える」能力は、高い方がいいに決まってますもんね。
コロナの時期で、実際に人と会うことが減りました。
今後は知り合いやお客さん、上司や取引先とのやり取りには、文章力がより重要になってきます。
文章力が身につくと、いいことがいっぱい!
SNSのフォロワーが増えた!
知り合いとのLINEのやりとりが、スムーズになった!
上司から「分かりやすい資料で助かったよ」とほめられた!
本業・副業の収入が増えた!

「人とうまくつながる」
「人間関係をより良くする」
「仕事に活かせる」
文章力が身に付けば、いいことがたくさんありますよね。
それでは具体的にどうすればいいのでしょうか?
読みやすい文章を作るためのコツ 6つ
結論を最初に書く。
例えば部下から上司へ、こんなメール。
件名
「来週の打ち合わせについて」
本文
お疲れ様です。○○です。先日は食事に誘っていただきありがとうございました。あんな高級ワインは初めて飲みました。つい飲みすぎてしまいましたが、ご迷惑をおかけしなかったでしょうか?また機会がありましたら、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、来週の打ち合わせについてですが、実は○○さんが今度の新規事業の内容について詳しいということを小耳に挟みました。ご本人に確認したところ、確かに詳しいと思いました。○○さんとは部署が違うのですが、同期の△△から偶然そういう話が聞けまして、ご本人に確認させて頂いた次第です。今度の新規事業につきましては、私も気合を入れて望んでいます。ぜひとも我が社の業績アップに貢献したいと考えております。、、、以下省略。
このメール、上司がイライラするだろう、ということが分かりますか?
それは、
・どんな要件なのか、さっぱり分からない。
・読み手の時間と体力を奪ってしまっている意識が感じられない。
というのが理由なんですね。
「えー、これくらいなら、自分もやってしまってる」という人。
大丈夫です。
改善例
件名
【提案】「来週の打ち合わせに○○さんもお呼びしてはどうでしょうか?」
本文
お疲れ様です。○○です。
先日は食事に誘って頂き、ありがとうございました。
また機会がありましたら、よろしくお願いいたします。
さて、来週の打ち合わせですが、○○さんもお呼びしてはどうでしょうか?
理由としましては、、、以下省略。
いかがでしょうか。圧倒的に読みやすくなったのが、分かると思います。
このように、
・伝えたいことを件名に書く。
・本文の序盤にも同じように書く。
こうするだけで、上司の機嫌を損ねずに済みますよ。
会話のパターンで「頭括型(とうかつがた)」「尾括型(びかつがた)」があります。
要点を最初に伝えるのが頭括型。
最後に伝えるのが尾括型。
普段の会話が尾括型になりがちな人(女性に多いそうです)は、文章でも同じ傾向があります。
素早く要件を伝えたいときは、要注意ですね。
余談:冒頭の挨拶 いる?いらない?
結論:相手との距離感次第。
例のメール冒頭にある、食事のくだり。
あなたはいりますか?いりませんか?
「以前の関わりについて、後日あらためてお礼を述べる」という習慣。
これは日本独特だそうです。
ですから、会ったときでもメールでも、「先日のこと、ありがとうございました」というくだりが発生するんですね。
個人的には、相手との距離感によって、したりしなかったりでいいと思います。
必ず入れなきゃいけないということはないです。
こまめに改行する。
上のメールの例で、こまめに改行したのですが、分かりましたか?
相手がスマホで見ることが分かっていたら、「。」の度に改行してもいいくらいですね。
ちなみにこのブログ、約80%のユーザーが、スマホから見ています。
この割合は、どのサイトでも大きくは変わらないと思います。
意味が固まっている数行は近づける。
上のメールの例では、挨拶のかたまりを近づけ、1行空けてから、用件のかたまりがスタートしていますよね。
こんな感じで、意味のかたまりが終わったら、1行空けて次の話題にいくのがいいです。
文末の表現を繰り返さない。
「〜です。〜です。〜です。」
こんな文が続くと、幼稚に見えてしまうという特徴があります。
ですから、
- 〜です
- 〜ます
- 〜しました
- 〜とのこと
- 体言止め(文末を「さて、次の気になるニュース」のように名詞、代名詞などの体言で終わる形)
こんな感じで、文末を意図的に使い分ける工夫ができると、大人びた知的な印象に変わります。
Twitterで練習する。
Twitterは1回のツイートにつき、140字までと決まっています。
これが絶妙な文字数で、練習にぴったり。
日頃のあれこれや、ニュースを見て思ったことなど、140字という制限の中で、自分の言葉を発するのは、いい練習になります。
内容を見られたくないなら、非公開設定にしましょう。
写真やイラスト、図やグラフを入れる。

写真を入れると、読み手が早く理解できたり、理解が深まったりします。
ちなみに上の写真は「今、文章力がメキメキ成長してるぜ、イエイ!」というイメージですね。
文字ばかりを見ていると疲れてくるので、脳の小休止という意味もあります。
まとめ
今回は「読みやすい文章を作るためのコツとは?」をお伝えしました。
LINEやSNS。
メールや資料、報告書。
ブログやWebライティング。
文字で分かりやすく伝えることができたら、
「人間関係がスムーズになり、仕事も人生もうまくいく」
すぐにできることがあると思うので、役立ててもらえれば幸いです。