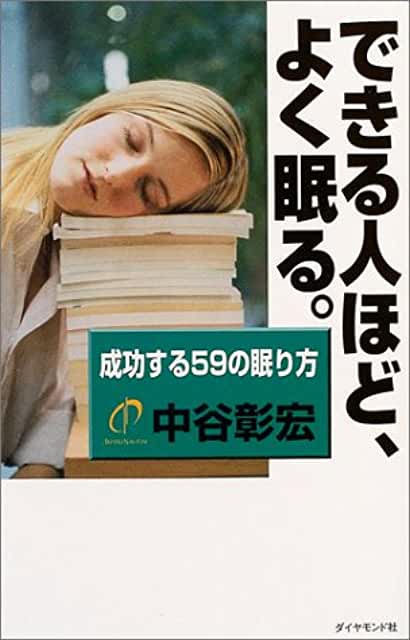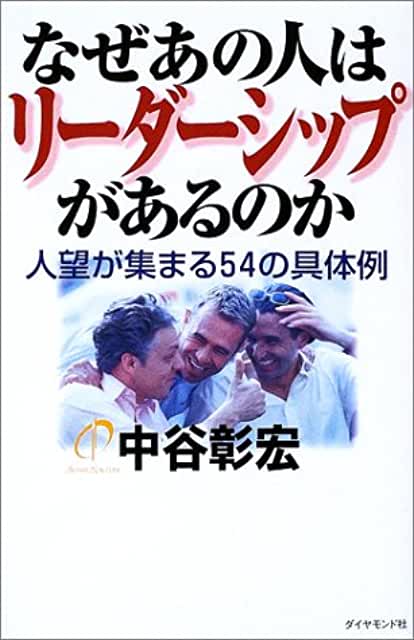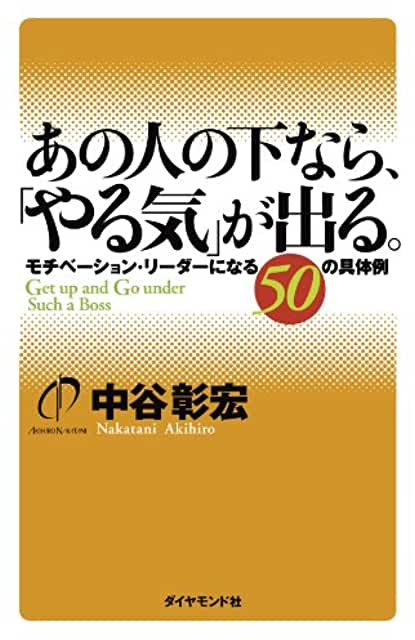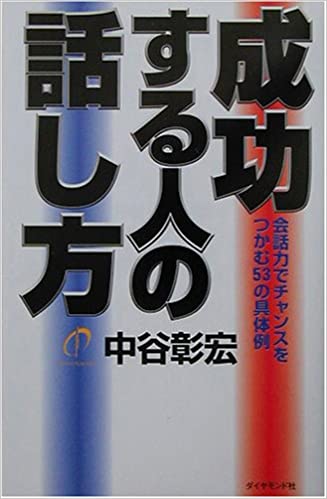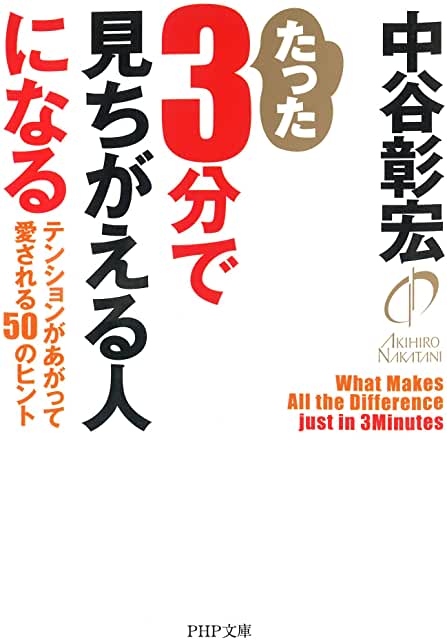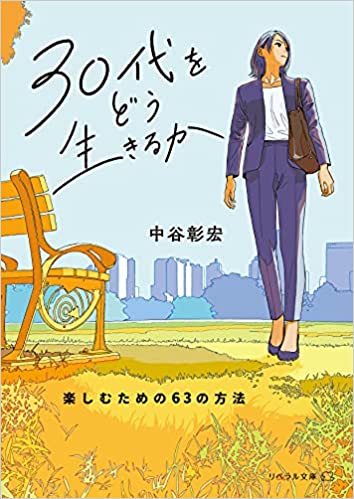「短くて説得力のある文章の書き方」[中谷彰宏](書き方=生き方だよね。)
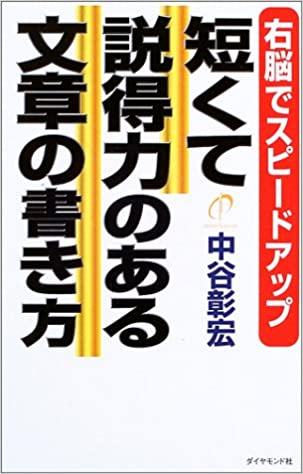
どうも、さっさです。
今回は中谷彰宏の「短くて説得力のある文章の書き方」から、ポイントをお伝えします。
・自分の文章に自信がない。
・「何が言いたいか分からない」「長い」と言われたことがあるが、どうしていいか分からない。
こんな感じで悩んでいる人、いますよね。
「。」がなかなか書けない人は、優柔不断であったり、リスクを回避することが多かったりします。
文字をびっしり書く人は、その頑張りがなかなか報われないで今まで生きてきた人です。
言い訳をする人は、おどおどして、常に予防線を張って生きてきた人です。
短くて説得力のある文章が書ければ、
・SNSでフォロワーが増えます。
・仕事で成果が出せるようになります。
・モテるようになります。(これは言い過ぎかな…でも分かりやすい人に、人が集まるのは事実ですからね。)
書き方を変えれば、生き方が変わります。
「書き方=生き方」なのです。
ポイントを6つ厳選して、さっさ的カバー。
「書くことが難しい」という人は、難しく書いているだけ。
結論:力まないで書いてみましょう。
書くことにまだ慣れていない人。
書くこと自体は、そうハードルの高いことではありません。
例えばSNSでフォロワーを増やしたいとか、ブログを書きたい、ゆくゆくは本を書きたいといったこと。
こんな時「どうやって書けばいいのか」と考え込んでしまいます。
でも、そう考えている時点で既に力んでいます。
カッコよく書こう、難しそうに書こうと思うから難しいのです。
論理的に、という発想はいったん捨てて、書きたいことから書き始めてしまいましょう。
思いついた順番が、一番分かりやすい。
結論:思いついた順番に書いてみましょう。結論は先に。
長めのメールや企画書を書く時には、構成はあまり考えない方がいいです。
構成を先に作ってしまうと、一番書きたいことが前に来ないからです。
人は話したいところから話します。
「すごかったんだよ」と話し出します。
話していくうちに、前に戻ったりするのです。
順番が前に行ったり、後に行ったり。こういう話が面白いのです。
歴史の授業では、戦国時代と幕末が面白いですから、そこから始めるようなものです。
読んでわかる言葉より、聞いてわかる言葉の方が、読んでも分かりやすい。
結論:目で書くのではなく、耳で書く。
広告には2通りあります。
①新聞・雑誌のような紙
②TV・ラジオのような電波
CMプランナーの人は、耳で聞いてわかる言葉を心がけています。
「そうだ 京都 行こう。」というのは、耳で読んでいます。
目で書いたら「京都に行こう」「京都へ行こう」となります。こう言う微妙な違いがあります。
アナウンス用語で「アバウト100」は「約100とは言いません。「およそ100」と言います。「約」が「100」に聞こえてしまうからです。
その聞き違いを予防するために「およそ」と言うのです。
読みやすく、速く伝わる文章があれば、それは耳で書いているからだといえます。
「読んでもらえる文章の書き方」は、学校も会社も教えてくれない。
結論:「書きかた」を学ぼう。
ビジネスマンの仕事のかなりの部分は、「書くこと」に費やされます。
メールにレポートに企画書など、振り返れば書いてばかりです。
学生や主婦でも「読み・書き・そろばん」という言葉があるくらいですから、誰にとっても書くことは大切です。
書くことはどう言うことなのか、学校でも会社でも教わりません。
教わらないのに、読書感想文なんてハードが宿題が出ます。
いい企画がひらめいても、企画書の書き方が下手なために、いつまでも通らないことがあります。
アイデアは企画書・稟議書で通さなければなりません。
アイデアの作り方を勉強するのと同じように、書き方を勉強するエネルギーも咲かなければいけません。
時間がない時の方が、いい文章が書ける。
結論:時間がない時ほど、書こう。
「書く時間がない」「まとまった時間さえ取れれば書けるのに」とグチをこぼす人がいます。
これでは一生書けません。
文章はお好み焼きと同じです。焼きすぎて固くなって、遅く出てきたお好み焼きにおいしいものはありません。いじくり過ぎているのです。
時間がなくてサッと走り書きした企画書には、無駄な言葉がありません。
時間がないと、面白い言葉、気持ちの入った言葉だけになります。
時間が経つと、気取った言葉や賢そうに見せる言葉が入ってしまって、本来の素直な言葉が埋もれてしまいます。
料理は出された瞬間からどんどん冷めていきます。
お好み焼きは焦げます。パスタは伸びます。
同じことが文章にも起こるのです。
流行作家の本が売れるのは、忙しいからです。忙しいので、文章をこねくり回すヒマがありません。
広告代理店に入る新人コピーライターは、つい「こんなことも知っているぞ」という難しい感じ、表現を使いたくなるワナにハマります。
でも、普通の言葉を使ってコピーを書くことがいかに難しいか、経験を積んでいくうちにわかってくるのです。
答えのすぐ出ないクイズ番組と文章は、見てもらえない。
結論:答えを先に書こう。
話が下手な人は、クイズ形式のやりとりをして、その答えをなかなか言わなくて引っ張ります。
テレビのトーク番組であれば「話がかったるい」と編集でカットされます。見ている人には面白くないからです。
フェイスブックやインスタのちょっとした投稿でも、答えまでの時間があまりにも長いと、読む人はそこまで気長に付き合ってくれません。
読む人はそれほどヒマではないのです。
書くときは、読み手の顔色がわからないので、書き手の性格がはっきり出てくるのです。
クイズ形式の文章は、答えを先に書きましょう。
まとめ
いかがでしたか。
「人にものを伝える」というのは、考えれば考えるほど難しいものです。
生きていくのに大事なスキルなのに、学校や会社では教えてくれません。
自分から学ぶしかないのです。