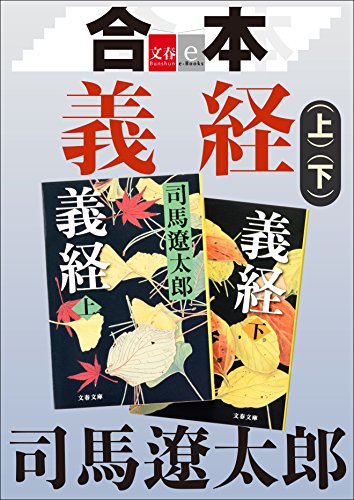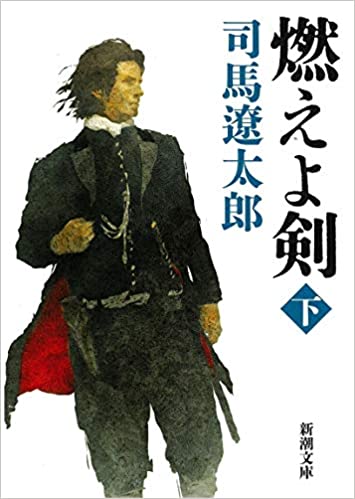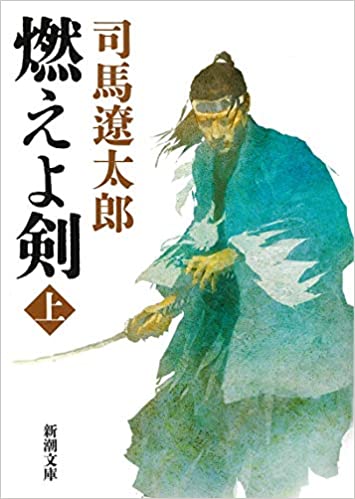【読了記録】国盗り物語(一)(二)/司馬遼太郎(戦国の革命児・斎藤道三がゆく!)
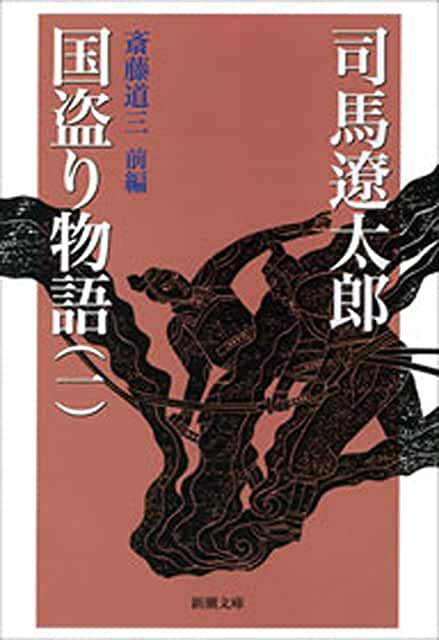
どうも、さっさです。
司馬遼太郎の小説『国盗り物語(一)(二)』を読みました。
学びや気づきを書き残します。
発行 1971年12月2日
読了 2022年7月25日
司馬遼太郎の読了履歴
『竜馬がゆく』
上司の勧めで8巻一気読み。幕末の状況が飲み込みにくかったものの、坂本龍馬の常識にとらわれない発想には、学べるところがあります。
『義経』
中2国語の教科書で「平家物語」があります。その副読本として紹介されていたので読みました。源氏、平氏、朝廷の立ち振る舞いが、現代でも参考になります。このサイトでも読了記録を書いています。
『燃えよ剣』
2021年10月の映画公開をきっかけに読みました。土方歳三の生き様に胸を打たれます。中学生の時に『るろ剣』人気ついでに手を出して、リタイヤしていました。このサイトでも読了記録を書いています。
そして、『国盗り物語』にたどり着きました。塾で歴史を教えている者として、司馬遼太郎は全制覇しておきたい。読んでいると、やはり授業中の言葉の乗りが全然違います。
あらすじと感想
世は戦国の初頭。松波庄九郎は妙覚寺で「知恵第一の法蓮房」と呼ばれたが、発心して還俗した。京の油商奈良屋の莫大な身代を乗っ取った庄九郎は、精力的かつ緻密な踏査によって、国乱れる美濃を<国盗り>の拠点と定めた! 戦国の革命児・斎藤道三が、一介の牢人から美濃国守・土岐頼芸の腹心として寵遇されるまでの若き日の策謀と活躍を、独自の史観と人間洞察で描いた壮大な歴史物語の緒編。
「BOOK」データベースより
斎藤道三は「松波庄九郎」としてスタート。名前が変わっていくのは、この時代あるあるですね。
弱体化している室町幕府を見て、日本を支配することを夢見ています。その発想と行動力は、令和に生きる人の胸を打つのではないでしょうか。
庄九郎はまず京都の油屋の女主人を口説いて、お金の蓄えを作ります。そして美濃(岐阜市あたり)に岐阜城を作って、一国の主となっていきます。
新しい土地でいきなり出世するのは難しいので、お金をばら撒いたり、権力者と仲良くなったり排除したりします。お金と陰謀を駆使してのしあがっていくのです。
美濃と京都の間には、幾つもの関所があり、通行料の支払いが必要です。でも斎藤道三は事前の計らいで、無料で通行できます。
何事も創意工夫が大好きで、武芸では槍術を生み出したと言われています。当時は刀と弓は一般的な武器でしたが、槍を操る人はいなかったそうです。
庄九郎の人生には目的がある。目的があってこその人生だと思っている。生きる意味とは、その目的に向かって進むことだ。
本文より
かっこいい。
現代では何になりたいか、何をやりたいかを悩む人がいかに多いことか。
「官位など、要りませぬな」
本文より
官位があったところで、戦国の世には何も意味がありません。たとえ関白になったところで、大軍が押し寄せてきたらそれまで。斎藤道三には官爵などは必要なかったのです。
斎藤道三には独自の道徳があります。自分の理想のためには、旧来の法や神仏に従順であっては、統一の大業を成し遂げられはしないと考えていました。
四十を越えると、妙なことがある。他人さまを平気できらいになってしまう。他人だけでなく、自分もふくめて、どれもこれも少しずつ峻烈に気に入らなくなってきた。
本文より
今、僕はちょうど40歳。これ、めちゃくちゃよく分かります。
父親が癌で55歳で亡くなったので、自分の人生ももうそんなに長くないのではないか、という前提があります。そうなると、面倒な他人は我慢できない。でも関わるのは面倒なので、徹底的に避ける。何か言ってくる人は強く言い返して、その後あまり言ってこないようにする。そんなふうになってきました。
これは、「人を避ける」というよりは「自分の人生を長く生きたい」からです。他人に合わせて生きるほど人生は長くないのです。そんな気持ちがこの時期の斎藤道三と重なります。
韓非子には、「人の君主たる者は、家来に物の好きこのみを見せてはならぬ」というくだりがある。家来がすぐそれに迎合するからだ。
本文より
これも参考になるなあ。
前の会社の上司に合わせて、登山やゴルフに決して少なくないお金と時間を費やした過去を思い出します。どちらも今はやっていないので、振り返ると結果「上司に合わせて」やっていました。
斎藤道三は多くの家来に囲まれていました。隙を見せてはいけない、と家来の前では厳格な大将でいるのでした。でも夜は酒と女にデレデレです。
まとめ
今回は司馬遼太郎の小説『国盗り物語(一)(二)』の読了記録でした。
司馬遼太郎の小説は正直最初は読みにくいです。しかし、自分の状況に当てはめながら読んでいくと、人間模様はいつの時代も変わらないのだと分かります。
結局、「富・名声・愛」への欲が人を進ませ、狂わせるのです。
司馬遼太郎の小説を読みながら、自分の生き方を振り返る。そして、今後の参考にする。
歴史小説を避けている人がいたら、それはもったいないことです。先人の道を簡単にインストールして、未来に活かせるわけですから、こんな素晴らしいものはありません。
さて、この小説は4巻まであります。3巻はいよいよ織田信長の登場です。
歴史上の人物の武勇伝はいったんお腹いっぱい。ですので、この後は他の小説にいきます。
でも、またいつか戻ってきます。
それでは、また。